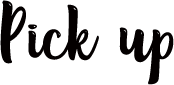2022.05.16
“学びのチャンスを逃さない”親の関わり方とは? アドバイスよりも子供に大切なこと[後編]
![“学びのチャンスを逃さない”親の関わり方とは? アドバイスよりも子供に大切なこと[後編]](https://fqkids.jp/wp-content/uploads/2022/04/fqk_sat20220426-ec2-290x220.jpg)
2025.07.04

青山鉄兵先生
 文教大学人間科学部准教授。文部科学省生涯学習調査官・国立青少年教育振興機構客員研究員・東京YMCA長期キャンプ「野尻学荘」副荘長などを兼務。専門は社会教育学、青少年教育論。
文教大学人間科学部准教授。文部科学省生涯学習調査官・国立青少年教育振興機構客員研究員・東京YMCA長期キャンプ「野尻学荘」副荘長などを兼務。専門は社会教育学、青少年教育論。
 「子どもの成長を支える20の体験」は、子どもの体験を考えるヒントとして、国立青少年教育振興機構が提唱し、文科省も推奨しているものです。
「子どもの成長を支える20の体験」は、子どもの体験を考えるヒントとして、国立青少年教育振興機構が提唱し、文科省も推奨しているものです。
「全部やらなきゃ」ではなく、「こういう体験もあるのか」と新しい選択肢に気付いたり、「こんな体験も大切なんだ」と日常の体験を見直すきっかけにしてみてくださいね。(青山先生)

●規則正しい生活
●遊び
●お手伝い
●家族行事
●運動・スポーツ
●読書
●動植物とのふれあい
●探究学習
早寝、早起き、朝ごはん、洗面、歯磨き、入浴など、基本的な生活習慣も、子どもの社会的自立に向けた大切な体験。大人にとっては当たり前のことでも、子どもの一生の健康を支える大切な学びのプロセスだ。
おにごっこやかくれんぼ、遊具や木登り、ごっこ遊びなど、自由な遊びを楽しむことは、質の高い体験そのもの。時には友達とのやり取りや摩擦が生じたり、けんかをして仲直りすることも、成長に欠かせない体験になる。
料理、掃除、皿洗い、洗濯物を畳むなどのお手伝いは、家族の一員としても自立へのチャレンジとしても大切。毎日決まったものを担当することで、責任感や自分なりの工夫が生まれることも。
家族で誕生日をお祝いしたり、年越し・お正月を一緒に過ごしたりすることは、家族の絆を深め季節を感じられる体験。ひな祭りや端午の節句などの季節行事はもちろん、大掃除なども親子で楽しんで取り組めると◎。
幼いうちは近所の公園で遊んだり、散歩したりするだけでも十分。成長してきたら、地域のスポーツ少年団、スポーツクラブ、部活動なども利用して。スポーツの試合を生で鑑賞することも体験としておすすめだ。
読書も体験の1つ。乳幼児期の読み聞かせから始まり、自分で読めるようになったらさまざまなジャンルの本を楽しむ機会を。一緒に近所の図書館に出かけたり、同じ空間でそれぞれ別の本を読んで過ごすのもおすすめ。
犬や猫、小動物などのペットを飼うのはもちろん、公園で捕った虫を飼育してみたり、植物を育てるのも多くの気付きが得られるはず。自然の中で野鳥や虫の観察をしたり、動物と触れ合える施設に出かけるのも楽しい。
探究学習というと難しそうに聞こえるが、日常のちょっとした疑問やフシギについて一緒に考えたり、調べたりしてみよう。2歳〜6歳頃に訪れる「なぜなぜ期」は探究学習の大チャンス。大人も一緒に楽しんで。

●家族との関わり
●友達との関わり
●先生との関わり
●地域との関わり
親にほめられたり叱られたり、一緒に遊んだり……最も身近な家族との関わりは、小さな子どもにとって大きな影響力を持つ。核家族化の現代では、祖父母やいとこなどと会う機会も大切にしたい。
子ども同士の関わりは、人と関わる力を育む上で欠かせない体験。一緒に楽しく遊ぶのはもちろん、けんかなど思い通りにいかない『ノイズ』の中で、子どもは成長していく。年齢が進むにつれ、友達の影響は大きくなる。
家族以外で、最も長い時間関わる大人が先生。先生に認められて嬉しかったり、仕事を任されてがんばったり、時には注意されたり、親とは異なる関係でのやり取りは、勉強だけでなくさまざまなことを学べる。
地域の多様な大人との関わりは、現代の子どもにとって貴重な経験。ボランティアの交通指導員さんと挨拶を交わしたり、住んでいる地域の町内会に入ってイベントに参加するなど、積極的に交流したい。
●自然体験
●集団活動
●地域行事
●社会貢献
●職業体験
●文化芸術体験
●科学体験
●国際交流体験
「20の体験」の“体験活動”について、具体的な提案を紹介する。普段の生活の中でできる日常の体験から、お出かけや長期休暇にやってみたいチャレンジな体験まで、子どもが興味のあることを見つける参考にしてもらいたい。
 近くの公園で遊んだりピクニックしたりするだけでも、身近な自然を体験できる。可能であれば、キャンプ、登山、カヌーやサイクリング、スキーなどを家族で楽しもう。子どもだけで参加するサマーキャンプなどの選択肢も。
近くの公園で遊んだりピクニックしたりするだけでも、身近な自然を体験できる。可能であれば、キャンプ、登山、カヌーやサイクリング、スキーなどを家族で楽しもう。子どもだけで参加するサマーキャンプなどの選択肢も。
日常
公園、お散歩、虫とり、近所の植物や鳥などの観察、植物の種まき
チャレンジ!
キャンプ、海遊び、川遊び、登山、カヌー・カヤック、スキー
 保育園や幼稚園、小学校などでの集団生活を通して、子どもは多くのことを学んでいく。できれば習い事や地域活動など、学校以外の集団を体験することも◎。周囲に認められたり、感謝されたりといった機会も増え、感情も豊かに育まれる。
保育園や幼稚園、小学校などでの集団生活を通して、子どもは多くのことを学んでいく。できれば習い事や地域活動など、学校以外の集団を体験することも◎。周囲に認められたり、感謝されたりといった機会も増え、感情も豊かに育まれる。
日常
保育園・幼稚園・学校に行く、友達と遊ぶ、習い事(グループレッスン)
チャレンジ!
子どもだけの体験ツアーやプログラムへの参加、宿泊施設の子ども向け体験プログラム
 地域のお祭りやイベントに参加することは、新しい出会いや交流のチャンス。地域のスポーツ大会や音楽祭などがあれば、気軽に多様な体験ができる。地域の伝統芸能や伝統行事に参加できれば、現代では貴重な体験に。
地域のお祭りやイベントに参加することは、新しい出会いや交流のチャンス。地域のスポーツ大会や音楽祭などがあれば、気軽に多様な体験ができる。地域の伝統芸能や伝統行事に参加できれば、現代では貴重な体験に。
日常
子ども会(町内会)、公民館・児童館・PTAなどのイベント
チャレンジ!
地域の伝統芸能、地域のお祭り
 子どもが社会貢献というとハードルが高そうに思えるが、学校や地域で行われる清掃活動や募金なども第一歩。自然環境、生き物、海外など、子どもが興味を持った分野でできるボランティア活動を調べてみることもおすすめだ。
子どもが社会貢献というとハードルが高そうに思えるが、学校や地域で行われる清掃活動や募金なども第一歩。自然環境、生き物、海外など、子どもが興味を持った分野でできるボランティア活動を調べてみることもおすすめだ。
日常
ゴミ拾い、募金、ペットボトルキャップ・使用済み切手などの回収活動への参加
チャレンジ!
ボランティア活動、高齢者施設などへお手紙・イラストを送る活動に参加、被災地支援・チャリティイベントへの参加
 近年は職業体験ができるテーマパークが増えており、子どもが楽しみながら世の中の仕組みや職業について学ぶことができる。長期休みなどに地域や企業が主催するプログラムも増えているので、ぜひチェックしておきたい。
近年は職業体験ができるテーマパークが増えており、子どもが楽しみながら世の中の仕組みや職業について学ぶことができる。長期休みなどに地域や企業が主催するプログラムも増えているので、ぜひチェックしておきたい。
日常
職業体験型テーマパーク、動画や絵本などで職業を知る
チャレンジ!
夏休みの子ども職業体験、地域や宿泊施設の農業・漁業体験イベント、家族のお仕事見学
 家でお絵かきしたり、ピアノやバレエなどの習い事に通ったりすることも、立派な文化芸術体験。美術館や、音楽・演劇・伝統芸能の鑑賞などは敷居が高いと思いがちだが、子連れで参加しやすい施設や企画の開催も多い。親子で楽しんでみて。
家でお絵かきしたり、ピアノやバレエなどの習い事に通ったりすることも、立派な文化芸術体験。美術館や、音楽・演劇・伝統芸能の鑑賞などは敷居が高いと思いがちだが、子連れで参加しやすい施設や企画の開催も多い。親子で楽しんでみて。
日常
お絵かき、音楽配信サービスやYouTubeでさまざまなジャンルを聴く、ピアノ・バレエなどの習い事
チャレンジ!
演劇観賞、演奏会観賞、落語・歌舞伎・能などに触れる、美術館
 家での工作や料理など、身近なものも科学体験の1つ。科学館などの施設に行けば、本格的な科学体験や科学ショーが楽しめる。プログラミングやロボット制作などの習い事や、自宅でできるキットも増えている。
家での工作や料理など、身近なものも科学体験の1つ。科学館などの施設に行けば、本格的な科学体験や科学ショーが楽しめる。プログラミングやロボット制作などの習い事や、自宅でできるキットも増えている。
日常
料理、おうち実験遊び、重曹や酢などを使った掃除
チャレンジ!
プログラミング体験・教室、ロボット作り体験・教室、科学館、実験ショー
 近年は国内でも国際交流の機会が増えている。園や学校に外国出身の子どもや親がいることも。海外旅行はもちろんだが、外国の料理を食べに行くなど気軽な体験でもOK。留学生のホストファミリーになるという選択肢もありだ。
近年は国内でも国際交流の機会が増えている。園や学校に外国出身の子どもや親がいることも。海外旅行はもちろんだが、外国の料理を食べに行くなど気軽な体験でもOK。留学生のホストファミリーになるという選択肢もありだ。
日常
異国料理を食べる、外国の絵本、外国人のクラスメイトと遊ぶ、英会話教室(オンライン含む)
チャレンジ!
ペンパル(文通)や海外の子どもとのビデオ通話交流、国際交流イベント、イングリッシュキャンプ、海外旅行、ホストファミリーになる
A.子どもが自分で興味を持ったものからやってみよう
どの体験が子どもにとって「質の高い体験」となるかはその子とタイミング次第。あまり教育的な意味については考えすぎず、子どもが興味を持ってやりたがることでOKです。
A.全部やろうとしなくてOK。焦らず、できるところから
「20 の体験」は全部やらなくてはならないということではなく、あくまで目安です。「次の休みに子どもと何しようかな?」という時に参考にしてみてください。
A.子どもの主体性を大切に、親も一緒に心から楽しむ
子どもが自ら「やりたい」「やろう」と主体的に取り組むことが、体験の質を高めます。親は子どもに何かやらせるというよりも、一緒に楽しんで関わってあげる方がおすすめです。
文:岡本いつか
FQ Kids VOL.22(2025年夏号)より転載