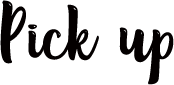2022.12.04
【STEAM教育2022】ロボット工学に役立つ幼児期の遊びって? 関わり方にコツも

2025.11.05

吉永安里さん
 國學院大學人間開発学部子ども支援学科教授。都内の私立幼稚園に勤務しながら教員免許を取得し、公立小学校、東京学芸大学附属小金井小学校教諭などを経て現職。幼稚園と小学校での教員経験から小学校入学で感じるギャップを自ら体感し、幼保小の接続について研究するに至る。専門は保育学、乳幼児教育学、国語教育学。幼保小接続に関する執筆、講演多数。
國學院大學人間開発学部子ども支援学科教授。都内の私立幼稚園に勤務しながら教員免許を取得し、公立小学校、東京学芸大学附属小金井小学校教諭などを経て現職。幼稚園と小学校での教員経験から小学校入学で感じるギャップを自ら体感し、幼保小の接続について研究するに至る。専門は保育学、乳幼児教育学、国語教育学。幼保小接続に関する執筆、講演多数。
幼児期から小学生への移行でつまずいてしまう小1プロブレム。
「子どもが0歳から18歳まで育つ過程の中でも、小1は最も段差・壁を大きく感じやすいタイミングです」と教えてくれたのは、國學院大學教授の吉永安里さんだ。
「幼児教育は、好きな遊びや生活での経験を通して総合的な学びをする『経験主義』が中心です。一方小学校では、限られた時間の中で効率的に学習するため、教科ごと内容の配列通りに学ぶ『系統主義』が中心となります。その根本的な違いが6歳の子どもには大きな段差となり、つまずくことが多いのです。
この問題に対し、文部科学省では子どもがもっと連続性・一貫性を持って育っていけるよう、小学校と保育園・幼稚園が連携したり、カリキュラムをつなげるさまざまな対策(幼保小接続・連携)を行ってきました。
近年は小1の始まりを幼児期のつながりから始めるという『スタートカリキュラム』や、低学年での『生活科』を中心とした教科を関連させた指導など、新しいカリキュラムのあり方の提案もしています。
なお、この一貫性のある育ちというのは子どもの将来的なウェルビーイングに関わることなので、小1だけの問題とせず、18歳までの育ちの過程の一部としての視点も大切です」。
その段差を小さくするために、幼児期に先取り学習のような早期教育をすればいいのではという疑問が湧くが、それは違うという。
「幼児期は、子どもが直接環境と関わり、体験を通して学ぶ時期です。特に遊びは重要で、遊びの中で気付いたり、不思議に思ったり、試行錯誤したり、友達と協力したりする喜びといった経験は、好奇心や創造性、文字・数への関心などの“学びの芽”となり、小学校以降の教科の学習につながります。
AIのさらなる進化が予想されるこれからの時代、求められるのは何事にも自分で興味を持ち、主体性を持って学び、仲間と対話をして問題解決していくことです。まさに幼児期の遊びにより養われる力そのものと言えるでしょう。
一方で、最近の幼児教育の現場では小1プロブレムを不安に思う保護者の早期教育を求める声が大きくなり、課題となっています。親が遊びの重要性を理解し、幼児期は幼児期の子どもにふさわしい環境をつくること。そして子の遊びに一緒になって興味を持ち、面白がり、関わり、その中にある学びの芽を伸ばすことが、一番大切な小学校への準備なのです」。
1 社会情緒的スキル(非認知能力)を育む
好奇心、思考力、粘り強さ、やり抜く力、人と協同する力 など人とコミュニケーションを取ったり、学びに向かうための力を育む
2 生活習慣を整える
食事、睡眠、排せつ、挨拶、片付け など基本的な生活習慣を通して、健康の土台や先を見通せる力を培う
3 認知的スキルへの興味を芽生えさせる
文字・数への関心 言葉への親しみ など文字や数を使って何かを知りたい、楽しみたいという気持ちを養う
幼児期は、遊びや生活を通してこの3つが育つことが大切! 「体験」を通して自然と育まれる“学びの芽”が小学校以降の学ぶ力の基礎になっていく
 1つの遊びの中だけでも、非常に多くの学びが育まれる。大人は遊び込める環境を用意してあげたり、子どもが主体的に遊んだりできるよう、受容的な関わり方をしてサポートしよう。幼児期は、毎日たくさんの経験を通して学びの芽を増やしていく時期だ。
1つの遊びの中だけでも、非常に多くの学びが育まれる。大人は遊び込める環境を用意してあげたり、子どもが主体的に遊んだりできるよう、受容的な関わり方をしてサポートしよう。幼児期は、毎日たくさんの経験を通して学びの芽を増やしていく時期だ。
 小学生の生活科の特別授業に保育園児が参加した様子。交流により園児は小学校を身近に感じられ、児童は園児との関わりで自分の成長や課題を実感できるなどのメリットがある。
小学生の生活科の特別授業に保育園児が参加した様子。交流により園児は小学校を身近に感じられ、児童は園児との関わりで自分の成長や課題を実感できるなどのメリットがある。
写真提供:横浜市立東本郷小学校、横浜市鴨居保育園
● 幼保小交流会
● 教員・保育者の合同研修
● 架け橋プログラム など
幼児と小学生が行う相互交流や教員同士の勤務体験、また、幼児教育と小学校教育のカリキュラムをつなぐ架け橋プログラムの作成など、さまざまな取り組みがされている。わが子が通う小学校ではどんな取り組みがされているのか、自治体のHPに載っていることもあるので、改めて確認してみよう。
上で解説した「3つのポイント」は、5歳児になったら突然できるようになるというものではなく、乳幼児期を通した積み重ねで育んでいくもの。親子で行うおすすめの取り組みを、吉永先生に教えてもらった。
社会情緒的スキル(非認知能力)
 好奇心、協調性、自己主張、自己抑制、頑張る力などの「学びに向かう力(非認知能力)」を成長させるには、幼児期に遊び込んだ経験が重要であるという研究結果がある。
好奇心、協調性、自己主張、自己抑制、頑張る力などの「学びに向かう力(非認知能力)」を成長させるには、幼児期に遊び込んだ経験が重要であるという研究結果がある。
さらに大人が強制したものでなく子どもが主体的にする遊びは意欲を生み、達成感を得ることができる。時間や環境の制約もあるが、親はできる限りわが子の遊びを見つめ、時にどうしたらやりたいことができるか一緒に考え、できる環境を整えてあげよう。
生活習慣
 小学校では授業、給食など時間に沿って区切りをつけることや、自分で立てた目標に向かう「調整能力」が必要。幼児期には睡眠、食事、排せつなどの正しい生活リズムの中で、先の見通しを持って行動する力を養いたい。
小学校では授業、給食など時間に沿って区切りをつけることや、自分で立てた目標に向かう「調整能力」が必要。幼児期には睡眠、食事、排せつなどの正しい生活リズムの中で、先の見通しを持って行動する力を養いたい。
3、4歳には「針がここにくるまでに片づけよう」、5歳には「夕飯は○時だから、それまでに何がやれるかな」など見通しが持てるような声掛けを心がけて。「○時に寝るために頑張ろう」と連帯感を持つのも楽しく取り組めるコツだ。
社会情緒的スキル(非認知能力)
 子ども達には、日々の生活の中で思うようにいかないことや失敗がたくさん訪れる。そんな時にすぐ諦めたり人に頼ろうとするのではなく、自分で挑戦することでレジリエンス(回復力)が育っていく。
子ども達には、日々の生活の中で思うようにいかないことや失敗がたくさん訪れる。そんな時にすぐ諦めたり人に頼ろうとするのではなく、自分で挑戦することでレジリエンス(回復力)が育っていく。
親にできるのは①先回りして全部やってしまおうとしないこと、②子どもの試行錯誤をそばで見守り、サポートすること、③「諦めないで頑張ったね」と認めてあげたり、「どうしたらできるかな」と一緒に困難に向き合ったりすることだ。
認知スキル
 大切なのは入学前に読み書き計算ができているかではなく、文字や数について子どもの関心が育っているかどうか。個人差はあるが、絵本の読み聞かせなどを通して自然と興味は生まれてくるもの。
大切なのは入学前に読み書き計算ができているかではなく、文字や数について子どもの関心が育っているかどうか。個人差はあるが、絵本の読み聞かせなどを通して自然と興味は生まれてくるもの。
少しでも興味の芽吹きを感じたら、手紙交換や交換日記、絵本、お手伝いなどの遊びや生活の中で子どもの「文字・数を使うと楽しい」気持ちを育もう。親は「どう書いたら伝わるかな」「家族4 人の箸を並べてね」と思考する場面を与えるような声掛けを。
社会情緒的スキル(非認知能力)
 子どもは“遊びの発明家”。大人が用意した既製のおもちゃで遊ぶよりも、牛乳パックや段ボールなどの廃材で工作をしたり、落ち葉や花、砂や石、水などの自然物で見立て遊びなどをしたりする時に、子どものインスピレーションや自ら遊びを創り出す力は高まる。
子どもは“遊びの発明家”。大人が用意した既製のおもちゃで遊ぶよりも、牛乳パックや段ボールなどの廃材で工作をしたり、落ち葉や花、砂や石、水などの自然物で見立て遊びなどをしたりする時に、子どものインスピレーションや自ら遊びを創り出す力は高まる。
また、廃材を収集したり片付けたりする過程で、環境問題を身近に感じることができたり、予測不能な自然に対し試行錯誤する中で感性が磨かれるなど、子どもが得られるものは多い。
文:松永敦子
FQ Kids VOL.21(2025年冬号)より転載