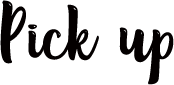2024.07.17
【0~6歳・年齢別】モンテッソーリ教育の「生活のおしごと」実践例&おすすめグッズ

2025.04.11

グローバル化が進む現在、教育を考える際にSTEAM教育の視点は欠かすことができない。STEAM教育とは単に「理工系を重視した教育」と認識されがちだが、本来の目的は問題を見出し、それを解決するための力を養うことにある。
「答えを教わるのではなく、自らの経験の中で試行錯誤しながら学ぶのがSTEAM教育です」と語るのは、全国キッズSTEAM教育協会で理事を務める石橋千明美さん。経験を重視するSTEAM教育では、失敗と成功をたくさん経験することで、失敗を恐れない子どもを育てることを目指している。
実体験を通じた学びは、記憶にも感覚にも残りやすい。深い知識と柔軟な思考力で、答えのない問いにも取り組める人材こそが、STEAM教育の目指す姿である。
 「Science(科学)」「Technology(技術)「Engineering(工学)」「Arts(芸術)」「Mathematics(数学)」の5文字を組み合わせた教育概念。
「Science(科学)」「Technology(技術)「Engineering(工学)」「Arts(芸術)」「Mathematics(数学)」の5文字を組み合わせた教育概念。
2000年頃にアメリカでSTEM教育としてスタートした後、自由な発想力・創造力に必要とされる「Arts」が加わり、STEAM教育として世界的に取り入れられている。複数の教科を横断的に学習するスタイルが特徴。
 複数の教科を総合的・横断的に学習することで、IT化が進む国際社会で通用する人材を育てることを目標としている。問題に対する答えを教師に教わるのではなく、自らの経験の中で失敗を重ねつつ、試行錯誤をしながらの学びを特徴とする。
複数の教科を総合的・横断的に学習することで、IT化が進む国際社会で通用する人材を育てることを目標としている。問題に対する答えを教師に教わるのではなく、自らの経験の中で失敗を重ねつつ、試行錯誤をしながらの学びを特徴とする。
 失敗と成功をたくさん経験することで、失敗を怖がらない子どもを育てる。答えがない問いにも取り組めるような自信を持たせるために、成功体験を重ねさせる。
失敗と成功をたくさん経験することで、失敗を怖がらない子どもを育てる。答えがない問いにも取り組めるような自信を持たせるために、成功体験を重ねさせる。
 現在、STEAM教育が世界的に注目されているのはなぜなのだろう。その答えは、世界中で拡大している不確実性にある。
現在、STEAM教育が世界的に注目されているのはなぜなのだろう。その答えは、世界中で拡大している不確実性にある。
ChatGPTを代表とするAIの登場により、世の中は予想もつかない改変期を迎えている。これまで以上のスピード感と不確実性、そしてさらなるグローバル化。現代を生きる子どもたちは、まさに予測不可能な社会を生き抜かなければならない。
「予測できない未来を生き抜く力を育てるには、これまでの知識を教えるだけでは不十分。新しい課題に対し、自分自身で考えられる思考力の育成が必要です」と石橋さん。
平成28年に決定された第5期科学技術基本計画では、人と物がテクノロジーとつながり、新たな価値を生み出す社会として「ソサエティ5.0」が提唱された。
AIの登場によって現存する職業の半分以上が不要となると予測されているが、「ソサエティ5.0」では、テクノロジーによって知識が共有され、人々が雑多な業務から解放されて、新たなイノベーションが生まれる社会が期待されている。
「現在子どもたちが学んでいるプログラミングや英語は、将来的にはAIに置き換えられる可能性が大きい。そうした社会では、テクノロジーをツールとして使いこなした上で、情報を集める能力や解読する能力が必要とされます」。
STEAM教育が目指す、未知の課題への対応力と解決力こそ、ソサエティ5.0に必要とされる能力だといえるだろう。
これからの世界に必要な能力として、4Cが挙げられる。これらは学校の成績などでは測ることができないが、他者と協働しながら、論理的に物事をとらえ、新しい考えを生み出すために欠かすことができない能力だ。

STEAM教育は、いつ頃始めるのが効果的なのだろうか?
「幼児期にスタートするのが理想的ですね」と石橋さん。その根拠に、STEAM教育の基盤の1つである「Growth Mindset(グロース・マインドセット)」の考え方がある。
この「グロース・マインドセット」は「成長型マインドセット」とも呼ばれる。親は「この子は理数系が得意」「この子は苦手」とつい子どもの能力を決めつけてしまいがちだが、「グロース・マインドセット」では、「能力は努力や方法によって変えられる」と考える。
幼児期からさまざまな体験を重ねることで「面白い」を経験し、「面白い」からこそ繰り返して、学びへとつながる。能力はこうした体験の積み重ねから育まれるため、幼少期に「面白い」「楽しい」時間を過ごすことは非常に大切だ。
また、幼児期にSTEAM教育によって、五感を使って学ぶことは、脳の発達にも極めて重要。幼児期からこの「グロース・マインドセット」を取り入れることは、高学年の学習にも良い影響を与えると考えられる。
マインドセットとは、心理状態や思考パターンの意味。これらのベースとなるのは、教育や経験に加え、思い込みや信念、先入観なども含められる。「リーダーになる素質は生まれつき」「理系科目には向き・不向きがある」「女子は数学が苦手」といった考え方は、思い込みや先入観によるマインドセットであり、「フィックスト・マインドセット」と呼ばれる。
STEAM教育では、この「フィックスト・マインドセット」とは対照的な「グロース・マインドセット」を重視しており、試行錯誤や体験を通しての学びを推奨している。
答えを教えない・先回りしない
 子どもが何かに興味を持ったとき、「すぐに答えを教えない」ことで思考力が育てられる。子どもが疑問を感じている時は、自身で答えを見つける過程を大切にすることで、子どもが課題を見いだし、その課題に対する答えを見つけられるようになる。先回りをせず、じっくりと寄り添うことが大切だ。
子どもが何かに興味を持ったとき、「すぐに答えを教えない」ことで思考力が育てられる。子どもが疑問を感じている時は、自身で答えを見つける過程を大切にすることで、子どもが課題を見いだし、その課題に対する答えを見つけられるようになる。先回りをせず、じっくりと寄り添うことが大切だ。
Trigger Words(トリガー・ワード)で「あえて反論」してみる
 子どもの「クリティカル・シンキング」やコミュニケーション能力を高めるためには、良質なディベートが効果的。子どもの主張に対して「どこが似てる?」「どこが違う?」「どうして?」といった「トリガー・ワード」であえて反論して議論を活発化させることで、深く考える力が育てられる。
子どもの「クリティカル・シンキング」やコミュニケーション能力を高めるためには、良質なディベートが効果的。子どもの主張に対して「どこが似てる?」「どこが違う?」「どうして?」といった「トリガー・ワード」であえて反論して議論を活発化させることで、深く考える力が育てられる。
「褒める」よりも「認める」
 子どもを褒める時も、褒め方が重要なポイントに。他人と比べるのではなく、「前はできなかった〇〇ができるようになったね」と以前の自分と比較することで、子どもは頑張った過程も認められたと感じられる。失敗した時は「F.A.I.L means “First Attempt In Learning”(失敗は学びの第一歩)」の考え方で、トライする姿勢を認めてあげよう。
子どもを褒める時も、褒め方が重要なポイントに。他人と比べるのではなく、「前はできなかった〇〇ができるようになったね」と以前の自分と比較することで、子どもは頑張った過程も認められたと感じられる。失敗した時は「F.A.I.L means “First Attempt In Learning”(失敗は学びの第一歩)」の考え方で、トライする姿勢を認めてあげよう。
「Not Yet(ノット・イェット)思考」で子どもを勇気づける
 「ノット・イェット」思考とは、「今はまだできていないだけ(これからできるようになる)」という、「できない」ことをポジティブにとらえる考え方。「ノット・イェット」思考を身につけることで、子どもは挑戦することが楽しみになり、「努力をすればできるようになる」というモチベーションにつながる。
「ノット・イェット」思考とは、「今はまだできていないだけ(これからできるようになる)」という、「できない」ことをポジティブにとらえる考え方。「ノット・イェット」思考を身につけることで、子どもは挑戦することが楽しみになり、「努力をすればできるようになる」というモチベーションにつながる。
全国キッズSTEAM教育協会理事
石橋千明美さん
 英語幼児STEAM教育「Pixi Academy」運営担当。上智大学卒業後、ボストン大学留学や外資系証券会社勤務を経て現職へ。NASA 提携Endeavor STEM Teaching Leadership Certificate候補。
英語幼児STEAM教育「Pixi Academy」運営担当。上智大学卒業後、ボストン大学留学や外資系証券会社勤務を経て現職へ。NASA 提携Endeavor STEM Teaching Leadership Certificate候補。
文:藤城明子
FQ Kids VOL.19(2024年夏号)より転載