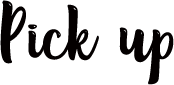2022.04.11
未来が変わる“お金”の教育『FQKids』2022年春号[VOL.10]
![未来が変わる“お金”の教育『FQKids』2022年春号[VOL.10]](https://fqkids.jp/wp-content/uploads/2022/04/FQKids10_800x600-290x220.jpg)
2025.05.09

食育という言葉が広く言われるようになって20年。「みんなが健康で幸せに暮らせるように」という目的は同じでも、そのためには栄養バランスよく、野菜を食べなきゃ、手作りしなきゃ、農業を知らなきゃなど、いくつもの「ねばならない」が叫ばれて、ちょっと苦しい時がありました。
今でも食育を「幼児のうちにあれもやらなきゃ、これもやらなきゃ」と頑張りすぎてしまう方に出会います。けれど、私たち大人が食で一番に伝えたいのは、一緒にテーブルを囲む人同士が「おいしいね」と笑顔になって、身体も心もあったかいエネルギーに満たされる充足感ではないでしょうか。
どんなごちそうも、栄養バランスが完璧な献立も、パパやママの笑顔にはかないません。「おいしいね」と目が合うひと時は、子どもたちの生涯の財産になり、作り手側の心さえも満たしてくれます。
細かな悪情報に振り回されず、まずは親自身が健康に育ったことに自信を持つ。そして今食べている食べ物を食卓の話題にしてください。ネタはテレビ、スーパーの棚、絵本、パパやママの思い出と、きっとたくさんあるはずです。そこで出た「?」は次の話題へとつながります。
親子で笑顔になれる!
おうち食育3つのポイント
1. にこにこ
残されたりすると「一生懸命作ったのに!」と思ってしまいがちですが、それが子どものプレッシャーになってしまうことも。手を抜いてもいいから、ママも一緒に座って、おいしそうな笑顔になって! それでも残されたら、ちょっとだけ悲しそうに見せて「またこの次ね」と下げちゃおう。
2. だいたい
栄養バランスをざっくり量でいうと、ご飯など主食が全体の半分、残りの3分の2が野菜、3分の1が肉・魚・卵などの主菜。ただし成長期はこれに牛乳・乳製品などタンパク質を多めにオン。朝のかたよりは昼食で、前日のかたよりは翌日に調整、くらいの気持ちで大丈夫。
3. いろいろ
家庭の食は、親の好みや力量の幅の中でしか再現できません。でも世の中にはたくさんの食材、料理、味つけがあり、人にはさまざまな好みがあることも伝えておきたいものです。グローバル社会で他者も尊重できるように、家の外の味に親子でチャレンジする機会はとても大事です。
「嫌い」ではなく「苦手」。それなら誰にもあることです。そして、何かのきっかけやアプローチの仕方で変化の可能性が期待できます。まずはそばにいる大人やお友だちがおいしそうに食べて見せること。手をつけないことがわかっていても、一口でもそばに置く。ソフトプッシュの根気はいつかきっと花開きます。
食事の前後や食卓回りに、好きなものがちらついていませんか。食事の時は、気の散る音は消して、おもちゃたちも「○○君がご飯食べるのを応援してるよ」と椅子に座らせる。それでも食べないときは、「はい、ごちそうさま」とさっさと片づけて次まで水分だけにしましょう。機嫌さえよければ心配無用です。
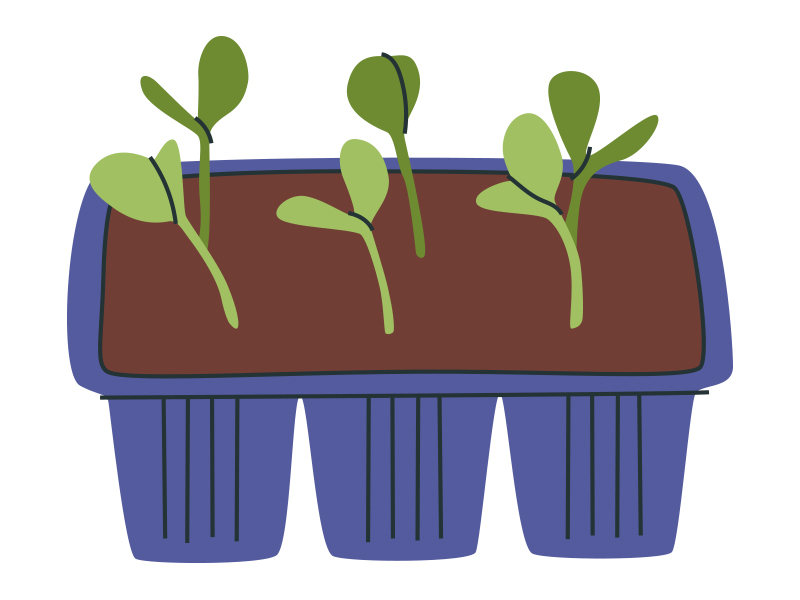 簡単なのはミニトマトやピーマン。初心者は苗からがおすすめ。苦手なものでも自分が育てたら食べたくなるものです。
簡単なのはミニトマトやピーマン。初心者は苗からがおすすめ。苦手なものでも自分が育てたら食べたくなるものです。
<がんばらないコツ>
がんばりすぎて水をやり過ぎるのが最も多い失敗例。2、3日おきに見守る程度が程よい距離感。ただし虫や病気は早めに見つけて対策を。1つでも実ができたら大成功。拍手です。
 キッチン仕事に興味を持ったときが食育適齢期。どんな結果でも「お手伝いしてくれた」と認めるところから。
キッチン仕事に興味を持ったときが食育適齢期。どんな結果でも「お手伝いしてくれた」と認めるところから。
<がんばらないコツ>
まずはレタスをちぎる、ボウルの中を混ぜるくらいから。肉や粉など飛び散って困るものは渡さないこと。簡単なのはお味見係。自分がかかわるとがぜん、食欲がわくようです。
現代社会では親も子どもも食の現場体験は乏しいものです。食の体験は子どものためというより、まずは親自身がやってみたいと思うプログラムに子どもを連れ出しましょう。子ども時代の一次体験は人生の肥やし。それが親子共有の思い出になれば一石二鳥です。
NPO法人食育研究会
Mogu Mogu代表理事
松成容子さん
 大学で食物学を専攻後、食業界専門の編集ライターに。自らの子育てを機に2003年、子育て世代で学び合う食育NPOを設立。現在では「畑からキッチンまで」の体験型食育活動のほか講演や執筆などで活動中。
大学で食物学を専攻後、食業界専門の編集ライターに。自らの子育てを機に2003年、子育て世代で学び合う食育NPOを設立。現在では「畑からキッチンまで」の体験型食育活動のほか講演や執筆などで活動中。
文:松成容子
FQ Kids VOL.20(2024年秋号)より転載