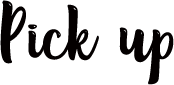2022.07.22
『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』特別インタビュー! 5人の活躍を支える幼少期の学びとは

2025.09.01
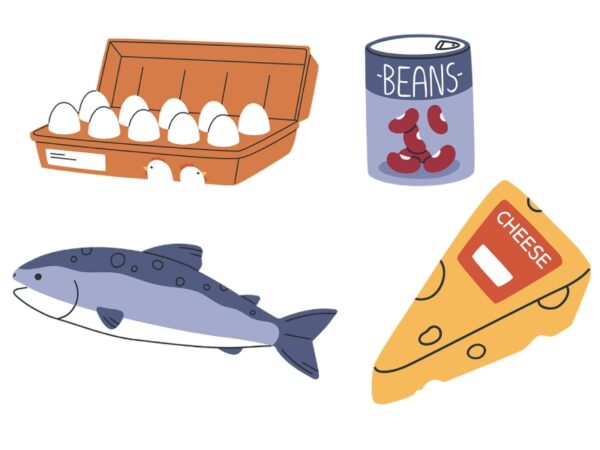
心身医療「内科」専門医
櫻本美輪子先生
 医療法人社団水青会小松川クリニック副院長。日本心身医学会 心身医療「内科」専門医。幅広い年代を対象として、分子栄養学に基づいた栄養療法を取り入れた医療を実践している。共著に『医師が教える子供の食事大全』(共著者/定真理子、ワニブックス)など。
医療法人社団水青会小松川クリニック副院長。日本心身医学会 心身医療「内科」専門医。幅広い年代を対象として、分子栄養学に基づいた栄養療法を取り入れた医療を実践している。共著に『医師が教える子供の食事大全』(共著者/定真理子、ワニブックス)など。
成長期にある子どもの体内では、すごいスピードで細胞分裂が繰り返され、大量の栄養素が必要とされる。この大切な時期に取りたい栄養素と食材についての知識を深め、毎日の献立づくりに役立てよう。
鶏・豚レバー、ウナギ、銀ダラ、ニンジン、ミカン
牛・豚・鶏レバー、ウナギ、カツオ、イワシ、サンマ
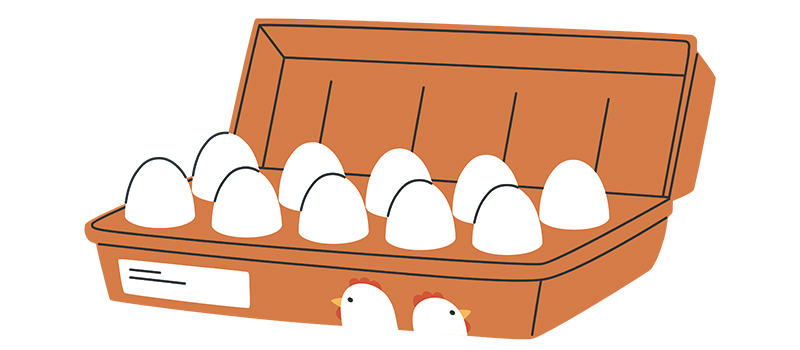 カツオ、ウナギ、イワシ、豚肉、鶏肉、牛肉、大豆、チーズ、卵
カツオ、ウナギ、イワシ、豚肉、鶏肉、牛肉、大豆、チーズ、卵
豚・鶏レバー、牛もも赤身肉、カツオ、イワシ
サケ、干しシイタケ、マッシュルーム、卵
イチゴ、赤ピーマン、ミニトマト
アーモンド、あおさ、わかめ、きな粉、豆腐(にがり使用)
カキ、牛肩赤身肉、レバー、カシューナッツ、たらこ
 ヨーグルト、小魚、チーズ、モロヘイヤ、木綿豆腐
ヨーグルト、小魚、チーズ、モロヘイヤ、木綿豆腐
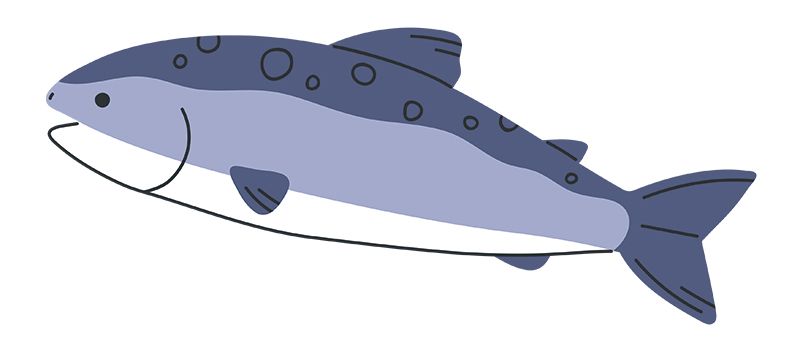 サンマ、イワシ、ハマチ、ウナギ、ブリ、アジ、サケ
サンマ、イワシ、ハマチ、ウナギ、ブリ、アジ、サケ
 大豆、ひじき、納豆
大豆、ひじき、納豆
 離乳食をスタートさせるのは、一般的に生後5~6ヶ月頃が目安とされている。しかし、「母乳は貴重な栄養素が含まれているので、離乳を急ぐ必要はありません」と櫻本先生。
離乳食をスタートさせるのは、一般的に生後5~6ヶ月頃が目安とされている。しかし、「母乳は貴重な栄養素が含まれているので、離乳を急ぐ必要はありません」と櫻本先生。
甘いジュースは血糖値が急に上がりすぎるので、果汁を与える時は果物を搾るか、小さく刻んで実ごと食べさせて。ただし、ビタミンCは野菜でも充分摂取できるので、無理に果汁を飲ませる必要はなく、水分補給は水や麦茶で十分。また腸管が未熟なケースもあるので、離乳食もシンプルな食材がおすすめだ。
 幼児食では、いろいろなたんぱく源を積極的に取り入れて。同じような献立が続くのは避け、肉も魚もバランスよく食べるのが理想的だ。市販の刺激的なおやつに舌が慣れてしまうと加工食品を欲しがり、食事を取らなくなることもあるので、おやつはシンプルなメニューを心がけよう。
幼児食では、いろいろなたんぱく源を積極的に取り入れて。同じような献立が続くのは避け、肉も魚もバランスよく食べるのが理想的だ。市販の刺激的なおやつに舌が慣れてしまうと加工食品を欲しがり、食事を取らなくなることもあるので、おやつはシンプルなメニューを心がけよう。
ご飯を食べる時はある程度時間を決めておくことで、「だらだら食い」を防止。子どものぐずりを防ぐために、「何となく」おやつやパンなどを与えるのは避けよう。
 ぐんぐんと背が伸び、身体が大きくなる小児期以降は、毎日しっかりたんぱく質を取ることが重要。卵焼き1切れでもいいので、おかずをつける習慣をつけたい。
ぐんぐんと背が伸び、身体が大きくなる小児期以降は、毎日しっかりたんぱく質を取ることが重要。卵焼き1切れでもいいので、おかずをつける習慣をつけたい。
また、脳の発達に欠かせないEPAやDHAを取るために、献立には魚も取り入れたい。しらす干しや小魚をサラダやおひたしにかけるだけでもOK。日常的に魚を食べさせて、魚好きに育てよう。亜鉛は身体と内臓の成長を促し、治癒力を高めるため、亜鉛を含むカキやレバーなどの食材もおすすめ。
子どもの食事や健康についてのよくある悩み。櫻本先生に分子栄養学の視点から答えていただいた。
A.胃酸の分泌量が不足してる?
分泌を促す栄養素を
 食べる量には個性がありますが、極端に食が細い場合は胃酸の分泌量が少なく、消化吸収能力が低下しているケースも。胃酸の分泌を促すカルシウムを、吸収力を高めるマグネシウムと一緒に摂取しましょう。牛乳はカルシウムは多くても、マグネシウムを含まないのでご注意ください。
食べる量には個性がありますが、極端に食が細い場合は胃酸の分泌量が少なく、消化吸収能力が低下しているケースも。胃酸の分泌を促すカルシウムを、吸収力を高めるマグネシウムと一緒に摂取しましょう。牛乳はカルシウムは多くても、マグネシウムを含まないのでご注意ください。
また、消化吸収能力が弱い子は、低血糖症である可能性も。たんぱく質中心の生活を心がけ、プロテインなども活用すると効果的です。身長が低いことが気になる場合は、ナッツ類や小魚で亜鉛を食事に取り入れましょう。
A.感情コントロールを助ける
栄養素を補給しよう
 感情をコントロールする脳内の神経伝達物質も栄養素からつくられます。「キレやすい」のは、脳内で調整の役割を果たすセロトニンや、興奮を抑えるGABAが不足しているサインかも。セロトニンやGABAの合成にはビタミンB群、とくにB6やナイアシンが重要です。子どものイライラを落ち着かせるためには、ビタミンB6や豚・牛レバーやたらこ、イワシ、サバなどに含まれるナイアシンを食事に取り入れましょう。
感情をコントロールする脳内の神経伝達物質も栄養素からつくられます。「キレやすい」のは、脳内で調整の役割を果たすセロトニンや、興奮を抑えるGABAが不足しているサインかも。セロトニンやGABAの合成にはビタミンB群、とくにB6やナイアシンが重要です。子どものイライラを落ち着かせるためには、ビタミンB6や豚・牛レバーやたらこ、イワシ、サバなどに含まれるナイアシンを食事に取り入れましょう。
鉄分不足でも情緒不安定や集中力低下につながることがあるので、ヘム鉄を多く含む赤身肉やレバー、カツオやイワシなどの食材を積極的に摂取してみるのもおすすめです。
A.サプリメントも活用して
腸内の環境を整えよう
快適な便通のためには、食物繊維が必須。食物繊維の多い大豆やひじき、納豆などを積極的に取り入れましょう。また、グルタミンは腸内環境を改善する作用があり、大豆製品や海藻などに含まれます。
腸内細菌のバランスを整えてくれるラクトフェリンを摂取するのも効果的。これは食事からの摂取が難しいため、できれば医療用のサプリメントを選び、空腹時や食間に飲むことがおすすめです。
A.ビタミンC&Dと
たんぱく質で体質改善
風邪などの感染症予防のために日頃から摂取しておきたいのが、ビタミンCとビタミンD。また、体内で抗体をつくるためにはたんぱく質も必要です。たんぱく質は皮膚や粘膜を丈夫にするので、感染症予防にも効果を発揮。
残念ながら風邪をひいてしまった時は、体力消耗を改善するビタミンCやビタミンB群を補給しましょう。
A.視覚情報をつかさどる
ロドプシンを再生する栄養素を
 最近はゲームやスマホで目を酷使している子が増え、網膜にあるロドプシンという色素が衰えがち。ロドプシンの正常な再生を促すためには、たんぱく質とビタミンAが必要です。
最近はゲームやスマホで目を酷使している子が増え、網膜にあるロドプシンという色素が衰えがち。ロドプシンの正常な再生を促すためには、たんぱく質とビタミンAが必要です。
ビタミンAは目の疲れやドライアイを改善する効果も備えています。ブルーベリーなどに含まれるアントシアニンも効果があるので、サプリメントなどで補給して。
A.肌の抵抗力をアップする
ビタミンAや亜鉛を補給
乾燥肌や湿疹が出やすい肌は、皮膚が弱くなっている証拠。皮膚を丈夫にするためには、肌をつくるたんぱく質が欠かせません。毎日しっかり取って十分な量を補給しましょう。
細胞が生まれ変わる時に必要な亜鉛は、皮膚の抵抗力をアップ。鳥・豚レバーやニンジンに含まれるビタミンAは、皮膚と粘膜を健康に保ち、不足すると傷つきやすくなるので、どちらもしっかり摂取を。
文:藤城明子
FQ Kids VOL.22(2025年夏号)より転載