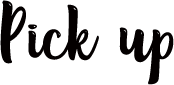2021.06.11
子供の才能を伸ばしてあげたいパパママ必見! カンタン「遺伝子検査サービス」登場

2025.09.05

4回シリーズでお届けするごきげん親子の視点づくり、今回が最終回。テーマは「生きやすく生きるためのプレゼント」である。
この先何が起きるかわからない世の中で、私たちは一体、子どもに何を残せるだろう。お金、家のような物理的なもの以上に、子どもたちの人生に大きな影響を与えるのは、感情の受け止め方やコミュニケーション能力ではないだろうか、と最近思う。
先日行った、とある飲食店での出来事である。個人経営の小さなお店だがかなりの人気店で、開店して5分後に到着した時には、すでに行列ができていた。10分くらい待っただろうか。私の後ろにも次々人が並びはじめた。
そこにおそらく、40代前半くらいの男女2人組(おそらくご夫婦)がやってきて、列に並ぼうとしたのだが、男性が突然「あ?!」と大きな声を上げた。「え? やってねーの?」思わず振り返ると、何やら壁沿いに置いてあるカラーコーンを見て大声を出しているようだった。
そのカラーコーンには「本日品切れにより閉店しました」と書いた札が貼ってあった。私が来た時には、壁際に裏返しになって置いてあったのだが、行列の誰かがぶつかったのか、壁から少し離れたところで斜めになっていた。どうやらそれを見てその人は閉店したのかと思ったようだ。
するとその人は肩を怒らせて店の入り口に向かい、扉を開けて、中にいる店員さんに向かって「ちょっと! 今日もう終わり?」と大きな声で聞いた。店員さんが「いえ、まだですが……」と答えると「じゃあなんなんだよあの札は!」と怒鳴った。
店員さんが表に出てきて、カラーコーンを確認し「あ、これは違います、申し訳ありません!」とカラーコーンを端に寄せ直したが、怒りが収まらず「なんなんだよ! わかりにくいんだよ!」とさらに怒鳴った。
「申し訳ありません」と小さくなる店員さんに向かって「こっちはわざわざ来てんだよ!」と追い打ちをかけるように声を荒げたところで、一緒にいた女性が「もういいから、まだやってるんだから並べばいいじゃない」と気まずそうな表情で止めに入り、店員さんも頭を下げながら店内に戻って行った。
そんな騒ぎの後私の番が来て、店内に入った。店員さんの接客も丁寧で、料理も評判通りボリュームもあってとてもおいしかった。食べ終えた頃、先ほど怒鳴っていた男性が女性と一緒に入ってきたが、2人とも、不機嫌そうな顔で会話もなくメニューを見ていた。
さて、ここまで読んだ読者の皆さんはどう感じただろう。人それぞれ感じ方は違うだろうが、今回は、「自分の子どもが成長した時に、男性のような行動をする大人になったとしたら、生きやすい人生を送れるかどうか」を考えていただきたいと思う。
 せっかくおいしい料理を、一緒に食べたい人と食べに来たのに、イライラして気分が悪くなって、一緒に来た人の気分も悪くして、無言で不機嫌な顔で食べるなんて、手に入れたかった未来ではないはずだ。きっとこの方は、今回だけではなく、他の似たような場面でも、同じように「怒り」を表に出してしまうことが多いのではないだろうか。
せっかくおいしい料理を、一緒に食べたい人と食べに来たのに、イライラして気分が悪くなって、一緒に来た人の気分も悪くして、無言で不機嫌な顔で食べるなんて、手に入れたかった未来ではないはずだ。きっとこの方は、今回だけではなく、他の似たような場面でも、同じように「怒り」を表に出してしまうことが多いのではないだろうか。
この方が本当に言いたかったことは、カラーコーンの置き方に対しての文句ではないと思うのだ。「自分は、ここで料理を食べることを楽しみにしてきました。でも、本日終了の札を見た時、もしかして食べられないのかな、と悲しい気持ちになりました」ということだったのだと思う。でも「なんなんだよ、わかりにくいんだよ!」では、その気持ちは1ミリも伝わらない。
もし自分だったらどうするか。もし、子どもが同じような場面に出くわした時、どう行動してほしいかを考えてみてほしい。
例えば「すいません、表に本日終了の札が出てるんですが、もう売り切れでしょうか?」と聞く。札が表に向いているのが間違いだったとわかったら「まだ大丈夫なんですね! 楽しみにしてきたので、間に合ってよかったです!」と言う。その後、一緒に並んでいる人と「よかったね、売り切れる前で! 何にしようか?」と楽しみにしながら待つことだってできる。
思い通りにならないことに対して「怒り」や「不満」をぶつける前に、「悲しい」「寂しい」「がっかりした」といったネガティブな感情を自分で受け止めること。
そして一方的に決めつけず、一見ネガティブな出来事の中にも喜びや感謝を見つけて、丁寧に人とコミュニケーションを取ることができるようになったら、もっと生きやすくなるのではないだろうか。
そのためには、まず親自身がその生き方を実践して、子どもの目の前でやってみせることだ。そしてもう1つ、子どもの感情を受け止めてあげること。
例えば、カッとなって友達に手を出してしまった時。妹が座っている椅子に座りたくて、突き飛ばしてしまった時。イライラしている時は難しいかもしれないが、冷静になったら「さっきはどんな気持ちだったの? 本当は、何をわかってほしかったの?」と聞いてみると良い。
「無視されて寂しかった」「座りたい場所を妹に取られて悲しかった」、それを怒りで表現しているのだとしたら、悲しい、寂しいという感情を伝えた方がわかってもらえるんだ、その感情を感じてもいいんだ、伝えても大丈夫なんだ、という経験させてあげるのだ。
自分が本当に感じている感情をきちんと味わうことができる人は、大人でもそういない。自分がイライラした時は、本当は何をわかってほしかったのだろう、と自分に聞いてみよう。出てきた感情を「本当は私は」を主語にして伝えてみよう。
子どもたちがより生きやすく生きられるように、まずは自分の生きにくさの原因に気づき、変えていくことが大切だ。子どもたちは大人が言い聞かせること以上に、普段実際にやっていることを見ている。笑顔で生きる大人がそばにいてくれることが、1番のプレゼントになるはずだ。最高のプレゼントを渡せる親になるために、このコラムがお役に立てば嬉しい。
鶴岡そらやす
 大学を卒業後、小中学校合わせて15年の教員生活の中で2000人以上の子どもたちと関わり、2014年、一念発起して退職し学習塾を開講。小、中、高校生の子どもたち、保護者へのコーチングにて問題発掘と課題解決を行う専門家として実績多数。大学生のキャリア支援メンター、高卒人財の就職支援、企業の新入社員研修などにも関わっている。2020年には親子で考える多様性についての書籍を出版。学校、教育委員会や、市民の集いなどで、生徒、教員、保護者への講演会を開催。小学校から社会人として自立するまでの発達段階を踏まえた、長期的視点からの子育てのポイントを伝えている。
大学を卒業後、小中学校合わせて15年の教員生活の中で2000人以上の子どもたちと関わり、2014年、一念発起して退職し学習塾を開講。小、中、高校生の子どもたち、保護者へのコーチングにて問題発掘と課題解決を行う専門家として実績多数。大学生のキャリア支援メンター、高卒人財の就職支援、企業の新入社員研修などにも関わっている。2020年には親子で考える多様性についての書籍を出版。学校、教育委員会や、市民の集いなどで、生徒、教員、保護者への講演会を開催。小学校から社会人として自立するまでの発達段階を踏まえた、長期的視点からの子育てのポイントを伝えている。
●Amebaブログ オフィシャルブロガー
●インスタグラムでは思春期の子どもとの関係づくりのコツを発信中! @sorayasunavi
FQ Kids VOL.20(2024年秋号)より転載