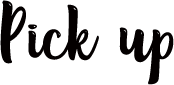2025.10.15
子育てファミリーの食事づくりを救う! 2025年注目の新製品アイテム5選

2025.09.01

子どもの身体がぐんぐんと大きく成長する乳幼児〜小児期。「健康に育てるには何を食べさせたらいいの?」「子どもが偏食で困っている」など、親にとって食事にまつわる悩みは尽きない。この大切な時期にふさわしい食事や生活について、栄養療法を取り入れた医療を実践する櫻本美輪子先生にお話を伺った。
櫻本先生が栄養療法のベースにしているのが、身体を構成する細胞を最適化するために、栄養素を活用する「分子整合栄養医学」。個々の症状に応じた食事指導で血糖値やたんぱく質などの摂取量を安定させたり、医療用サプリメントで代謝トラブルを解消したり、生活改善を行ったりすることで、身体や心の不具合を改善させる。
「私たちの身体は、およそ37兆個の細胞でつくられています。この細胞を構成しているのが、ビタミンやミネラルといった栄養素。これらの栄養素が不足することで身体に不具合が生じることがあるので、分子栄養学ではまず血液検査で不足している栄養素を調べ、不調の原因を調べます」。
例えば頭痛の原因としては、脳腫瘍などの重篤な疾患も考えられるが、実はビタミンや鉄などの栄養素不足でも起こりうる。身体の機能を正常に機能させ、健康的な成長を促すためには、十分な栄養素が欠かせないのだ。
「幼少期の健康な成長の基本となるのは、食生活とライフスタイル。身体が必要とする栄養素を体内に入れること、また不要な物を入れないことが大切です」と櫻本先生。
栄養療法は医学的治療であり、単に「子どもにとってバランスのよい食事」を目指すものではない。しかし、子どもの発育に必要とされる栄養素を理解し、献立に生かすことは、健康的な成長を促し、病気の予防にもつながる。
最新の医学に裏づけされた栄養素についての正しい知識を身につけ、これまで何となく作ってきた「バランスのよい献立」についても見直してみよう。

正式名は「分子整合栄養医学」。分子栄養学とも、オーソモレキュラー療法とも呼ばれる。血液検査などによって栄養素の過不足や代謝機能の問題点を突き止め、食事やライフスタイルの指導、医療用サプリメントや点滴などを用いて、細胞レベルで栄養状態の最適化を行う。
近年注目されている「糖質制限」。過去のダイエットでは食事のカロリーを制限することが多かったが、最近では肥満の原因をカロリーだけではなく糖質にあると考え、糖質の摂取を制限する傾向にある。
ただし、メディアやネット上で流布される糖質制限には誤った情報も多く、極端な食事制限を行うことが不調の原因となることも。まずは正しい栄養の知識を持つことが必要だ。
油を健康的な生活やヘルシーな食事の「敵」と考える人は多いが、実は油は成長期の強い味方。特に、EPAやDHAといった青魚に含まれる油は脳の発達に欠かせない栄養素であり、成長期はもちろん、生涯を通じて積極的に摂取したい栄養素だ。
カロリーが高い食品として警戒されがちなバターも、ビタミンA、D、Eを豊富に含む優秀な食品。成長を促し、免疫力強化につながるので、成長期の食事にぜひ取り入れてほしい。
「うちの子はなんだか疲れやすい」「最近子どもがよくイライラしている」「風邪をひきやすい」。こうした病院に行くほどではない子育てのトラブルも、実は栄養不足が原因であるケースは多いという。
子どもの不調の原因としてよく挙げられるのが、低血糖症。「情緒不安定」「感情の起伏が激しい」といった子どもが、実は血糖値の影響を受けていることがある。こうしたケースは甘いものや糖質の取り過ぎによって起こることが多いので、食事やおやつの内容を改善することで症状は緩和する。
成長期に必須のたんぱく質が不足しているケースでは、風邪をひきやすくなったり、疲れやすくなることも。また鉄分が不足している子どもは健康状態が不安定になることが多く、イライラしたり、朝起きられないといった現象にもつながる。
下図は子どもに多く見られる5つの栄養障害をまとめたもの。「原因はわからないが何となく不調を感じる」といった場合、こうした栄養障害が原因となっていることもあるので、不足している栄養素を突き止め、栄養不足の解消を心がけることで、トラブルを解消することができる。
たんぱく質は人の身体を構成する原材料。子どもの身体の成長には大量のたんぱく質が必要となるため、これが不足すると風邪などの感染症にかかりやすくなったり、疲れやすくなったりする。
「野菜中心の献立」はヘルシーなイメージだが、成長期の食事には肉、魚や卵が必須。豆類などの植物性たんぱく質を合わせるのもおすすめ。
低血糖というと糖分不足と勘違いされやすいが、低血糖症とは糖分の取りすぎによって血糖値が急激に上がり、反動で急激に下がる症状のこと。
甘いお菓子やスナック類の摂りすぎ、またおかずよりも白米やパン、麺類などを好む子どもによく見られ、気分のむらや睡眠の質の低下、無気力、情緒不安定などの症状につながる。空腹時はナッツなどを食べることで、糖分や糖質の取りすぎを抑えよう。
鉄は赤血球の原料として、ミネラルの中でも非常に重要な栄養素。身体全体を構成する細胞に必要とされており、鉄不足の状況では食事をエネルギーに変えることができず、集中力の低下や落ち着きのなさにつながる。
ヘム鉄を多く含む赤身肉やレバー、カツオやイワシといった動物性食品をビタミンCと合わせることで、効率よく鉄分を摂取できる。
ビタミンDは骨の発育に欠かすことができない栄養素。免疫機能を健全に保つ効果も備えているため、不足すると感染症にかかりやすくなり、花粉症などのアレルギー疾患が悪化することも。
またビタミンDはセロトニンの減少を抑制して感情のバランスを保つので、情緒の発育にも大きく影響する。生成には紫外線も必要なので、適度な外遊びを心がけて。
ビタミンB群はエネルギーの代謝に重要な役割を果たすため、不足すると血糖値が適正に維持できず、疲労感やイライラ、不眠、肌荒れなどの原因となる。
知能の発達や学習力の向上にも効果があり、特に乳幼児期に摂取したい栄養素。糖質や糖分を大量に摂取するとビタミンB群を消耗してしまうので、血糖値が急激に上がらない食事を心がけよう。

「身体によい食事を」と思っても、なかなか思い通りに食べてもらえないという悩みを持つ親は多い。それでも、日々の献立づくりや食べ方の工夫で、身体に必要な栄養素を効果的に摂ることができる。
「例えばおやつなら、焼き芋など素材の形ができるだけ残っているメニューがおすすめ。原料がわかりやすい煎餅などもいいですね」と櫻本先生。おやつでも食事でも、加工食品は味つけが濃いものが多く、味覚が不完全な段階から刺激を与えすぎるとシンプルな食材に満足できなくなるので、なるべく避けるのがベターだ。
忙しい朝食時も、パンやおにぎりに1品だけでもおかずを加えて、血糖の上がりすぎを防ごう。
動物性たんぱく質は植物性たんぱく質よりも圧倒的に吸収率が高く、成長期の子どもの食卓には肉・魚・卵が欠かせない。「野菜中心=健康的」とイメージする人も多いが、たんぱく質は体内にためておくことができないので、日々積極的に摂取したい。
スナック菓子に慣れてしまうと薄味では満足できなくなるので、シンプルな食材のおやつがおすすめ。また砂糖の取りすぎは体内の血糖が急激に上がり、低血糖症にもなりかねない。焼き芋にビタミンAが豊富なバターを組み合わせるなど、自然の甘さを楽しんで。
腸は第二の脳とも呼ばれる大切な器官。下痢や便秘といった腸の不調が続くと心にも大きく影響して、やる気や落ち着きがなくなることも。腸の健康を維持するためには、納豆やぬか漬け、みそ、しょうゆ、キムチといった発酵食品を積極的に食事に取り入れよう。
慌ただしい朝は、パンやおにぎりといった簡単メニューになりがち。でも炭水化物には糖質が多く、それのみでは血糖が上がりすぎるので、少なくともあと1品のおかずをプラスしたい。果物を入れた無糖ヨーグルトや、具だくさんのみそ汁などは、ビタミンやたんぱく質を簡単に補給できる。
食事を取る時はよく噛み、ゆっくり時間をかけることが大切。食べ始めてから「お腹がいっぱい」と満腹中枢からサインが出るまでおよそ15分かかるので、急いで食べると必要以上に食べ過ぎることになりがちだ。よく噛む習慣は脳に刺激を与え、思考力もアップする。
栄養療法では、体内に不足している栄養素を補給するためにサプリメントを処方されることがある。ただし、そうしたサプリメントは医療用のもの。ドラッグストアなどで販売されているサプリメントは「健康食品」で、栄養成分の含有用も大きく異なる。
市販品はあくまで健康維持のためのサポートと考え、身体の不調が出ていて食事だけでは改善しないような場合は、まず医師に相談しよう。
心身医療「内科」専門医
櫻本美輪子先生
 医療法人社団水青会小松川クリニック副院長。日本心身医学会 心身医療「内科」専門医。幅広い年代を対象として、分子栄養学に基づいた栄養療法を取り入れた医療を実践している。共著に『医師が教える子供の食事大全』(共著者/定真理子、ワニブックス)など。
医療法人社団水青会小松川クリニック副院長。日本心身医学会 心身医療「内科」専門医。幅広い年代を対象として、分子栄養学に基づいた栄養療法を取り入れた医療を実践している。共著に『医師が教える子供の食事大全』(共著者/定真理子、ワニブックス)など。
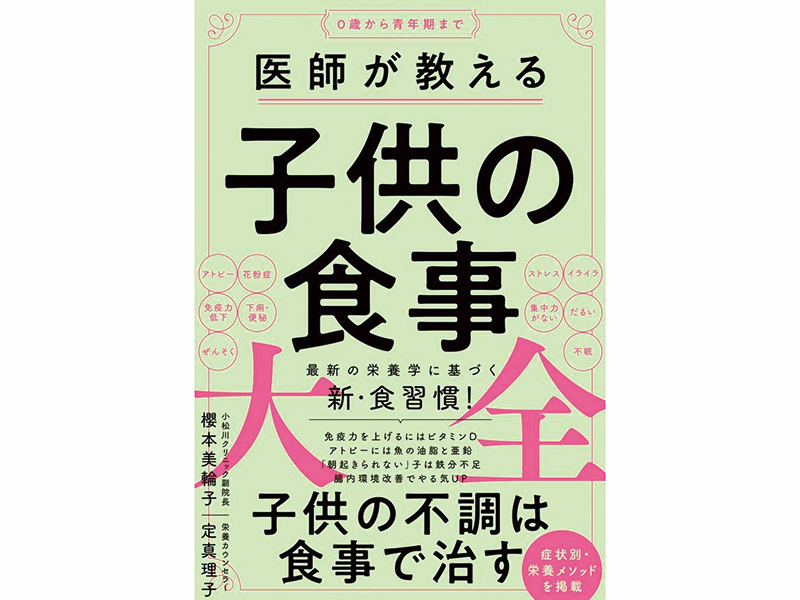
文:藤城明子
FQ Kids VOL.22(2025年夏号)より転載