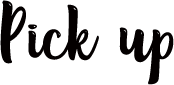2020.02.27
「優しい子に育ってほしい」という親の想いを応援。子供の思いやりを育むアプリとは?

2025.11.10

 習い事は、技術を身につけるためだけのものではない。日本の教育は学力向上において世界トップクラスとなったが、次のステップとして「子どもの生きる力の育み」が求められている。だからこそ、習い事には、自己肯定感やレジリエンス、継続力などの非認知能力を育てる役割が期待される。
習い事は、技術を身につけるためだけのものではない。日本の教育は学力向上において世界トップクラスとなったが、次のステップとして「子どもの生きる力の育み」が求められている。だからこそ、習い事には、自己肯定感やレジリエンス、継続力などの非認知能力を育てる役割が期待される。
グローバル人材を育てる英語教育プログラム「TLCフォニックス」を開発した船津徹氏は、次のように指摘する。
「日本では、弱点克服を目標として習い事を選んで失敗する例が少なくありません。例えば、子どもに落ち着きがないから、そろばん教室に入れるなどのケースです。
やんちゃで身体を動かすのが好きな子どもにそろばん教室はミスマッチとなり、技能の習得が遅くなることがあります。すると、子どもは 『自分は劣っている』と感じ、自信を失いかねません」。
では、そういう子にスポーツを習わせたらどうなるだろうか。屋外で思いっ切り身体を動かせるようなアウトドア活動でもよい。そういう習い事においては、たくさん動き回って怒られないどころか、「体力があるね!」と褒められる機会が増えそうだ。すると、子ども自身も嬉しく思い、技能の習得も早くなるだろう。
習い事の本質は、将来の仕事に直結するスキルを身につけることではない。大谷翔平選手のように、特別な才能と肉体を持って生まれたのならプロを目指すのも1つの道だが、多くの子どもにとっては、習い事を通じて得られる成功体験が重要である。
他者と協力し円滑に物事を進める能力である。小学校以降は、グループ活動やクラブ活動などで、家族以外の人と交流することで育まれる。チームスポーツは特に効果的で、チームメイトとの連携や共同目標の達成を通じて協調性が育まれる。グループで取り組むボランティア活動なども、協調性を高める良い機会となる。
 物事を続ける力を指す。この能力を育むためには、目標設定とその達成に向けた努力が必要である。一つ決めたらそれをやり遂げること、ルーティン化が重要である。子どもにはまだ難しいので、親がペースメーカーとなる必要がある。例えば読書の習慣づけをするなら、1日5~10分は必ず読書させるなどして、習慣化を促そう。
物事を続ける力を指す。この能力を育むためには、目標設定とその達成に向けた努力が必要である。一つ決めたらそれをやり遂げること、ルーティン化が重要である。子どもにはまだ難しいので、親がペースメーカーとなる必要がある。例えば読書の習慣づけをするなら、1日5~10分は必ず読書させるなどして、習慣化を促そう。
自分に対する肯定的な感情のこと。幼児期には、親からの無条件の愛情により育まれる。学童期になっても、「一生懸命やっているあなたを誇りに思う」と伝え続けることが大切。中学生以上でも自信を喪失することがあるので、「自信の補充」を行ってあげたい。いじけている時は抱きしめたり、頭をなでたりすると回復しやすい。
 習い事選びは、幼児期と小学校以降とで分けて考える必要がある。指先や手先の細かい動きを指す「ファインモータースキル(FMS)」という言葉が注目を集めるようになった。幼児期の習い事では、こうした指先や手先の力を鍛えることが重要である。
習い事選びは、幼児期と小学校以降とで分けて考える必要がある。指先や手先の細かい動きを指す「ファインモータースキル(FMS)」という言葉が注目を集めるようになった。幼児期の習い事では、こうした指先や手先の力を鍛えることが重要である。
粘土遊びやブロック遊び、お絵描きなどが効果的だ。小学校以降、本格的な学習が始まってからきっと役立つだろう。デジタル化が進む現代だからこそ、紙に書く訓練が求められる。
「指先や手先が弱い子が多くなっていると感じます。自然の中で土遊びをしたり、植物を引っこ抜いたりなどといった体験をする環境が減っているからでしょうか。だから、ジャングルジムでも公園でも、身体を使う運動をしてほしいですね。
本来は日本人が得意な領域ですし、大いにやらせるべきだと思います。脳の回線づくりにもつながって、思考力が豊かになります。幼児期からお絵描きや点つなぎなどを通して、手先の訓練をしておくといいと思います」
また、幼児期の習い事では競争は必要ない。大切なのは、「何があっても自分は親に愛されている」という実感だ。親が子どもに対して無条件の愛情と信頼を示すことが、自己肯定感の基盤となる。こればかりは、いくら自分が頑張っても得られるものではない。
一方で、小学校以降は、スポーツなら大会出場、音楽ならコンテスト挑戦など、具体的な目標を設定させることが成長につながる。ただし、次の船津氏のアドバイスも心に留めておこう。
「重要なのは、競い合いができるレベルまで引き上げてから競争やコンテストに出してあげることです。練習が不十分なのに、いきなりハイレベルな大会に出させることはやめてください。常に負けるレベルで競争させるのはかわいそうです。実力に合った競争での成功を目指して、努力して成功体験を積ませることが大事です。
とはいえ、どんな大会でも優勝するのは1人だけ。いい勝負をした上で負ける経験も大切だという。「負けた体験からどう立ち直るか、どうしたら次は勝てるのかを考えさせましょう」。
主役は常に子どもであるが、どの段階でも親のサポートは欠かせない。習い事を通じて、健全な競争心や挫折から立ち直るレジリエンスを身につけられるよう、子どもの様子を観察し、適切な環境を提供することが重要である。
船津徹さん
 1966年福岡県生まれ。明治大学経営学部卒業後、金融会社勤務を経て幼児教育会社に勤務。その後独立し、アメリカハワイ州に移住。2001年ホノルルにTLC for Kidsを設立。世界で活躍できるグローバル人材を育てるための英語教育プログラム「TLC フォニックス」を開発。最新刊『「強み」を生み出す育て方』(ダイヤモンド社)は現在8刷。
1966年福岡県生まれ。明治大学経営学部卒業後、金融会社勤務を経て幼児教育会社に勤務。その後独立し、アメリカハワイ州に移住。2001年ホノルルにTLC for Kidsを設立。世界で活躍できるグローバル人材を育てるための英語教育プログラム「TLC フォニックス」を開発。最新刊『「強み」を生み出す育て方』(ダイヤモンド社)は現在8刷。

文:木村悦子
FQ Kids VOL.21(2025年冬号)より転載