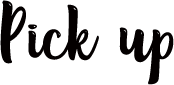2023.10.05
何回言っても「お友達のおもちゃを奪ってしまう」3歳児。必要な経験と声かけのコツ

2025.07.16

厚生労働省による「令和4年生活のしづらさなどに関する調査」では、日本に聴覚障害者が約37万9千人いることがわかっている。だが、現在彼らがどのような医療や支援を受けているのか、知らない人も多いのではないだろうか。
2025年6月29日、2025大阪・関西万博のオーストラリア館で、「パワーオブスピーチ~きこえる世界、わたしの選択肢~」というイベントが開催された。主催はオーストラリアの難聴児支援団体「シェパードセンター」。
日豪から聴覚医療・言語教育のリーダー、難聴当事者、家族が集結し、「聴覚障害者がよりよく生きる未来を考える」ために語られた内容をレポートする。
 イベントは、2025大阪・関西万博オーストラリア総合代表のナンシー・ゴードン氏の挨拶でスタートした。「オーストラリアパビリオンでは、誰もが共に学ぶ共に参加できる社会の実現を目指して、インクルージョンとアクセサビリティの価値を大切にしています」と語るゴードン氏自身、2歳の時にシェパードセンターの幼稚園に通った経験を持つ。
イベントは、2025大阪・関西万博オーストラリア総合代表のナンシー・ゴードン氏の挨拶でスタートした。「オーストラリアパビリオンでは、誰もが共に学ぶ共に参加できる社会の実現を目指して、インクルージョンとアクセサビリティの価値を大切にしています」と語るゴードン氏自身、2歳の時にシェパードセンターの幼稚園に通った経験を持つ。
「私の叔父は生まれつき聴覚障害がありますが、コミュニケーション能力に長けたリーダーとして活躍し、国の聴覚障害者バスケットボールチームのキャプテンも務めていました。音楽のビートを振動で感じ取って踊ることもできる優れたダンサーでもありました」と、聴覚障害を持つ人々がさまざまな分野で活躍できることを実証する体験談を語った。
 続いて、自由民主党難聴対策推進議員連盟事務局長の自見はなこ参議院議員は、日本の聴覚障害支援の現状について詳しく説明した。
続いて、自由民主党難聴対策推進議員連盟事務局長の自見はなこ参議院議員は、日本の聴覚障害支援の現状について詳しく説明した。
「2019年4月に議員連盟を設立し、『ジャパンヒアリングビジョン』を打ち出しました。新生児期からの早期発見・早期医療介入はもとより、全世代型の難聴対策を目指すものです」。
具体的な成果として、新生児聴覚スクリーニングの受診率が80%から96%に向上し、公費負担による検査を実施する自治体も22.6%から90%を超えるまでに拡大したという。
また、人工内耳※の適用年齢も従来の1歳から「1歳または体重8kg以上」に変更され、より多くの子どもたちが早期に人工内耳の恩恵を受けられるようになった。
※神経に直接信号を送り、音として認識させる医療機器(参考:日本財団ジャーナル「人工内耳って?補聴器と何が違う?その仕組みと「聞こえ」の大切さを専門家に聞いた」)
 日本耳鼻咽喉科頭顎部外科学会理事長の大森孝一教授は、人工内耳技術の発展について語った。
日本耳鼻咽喉科頭顎部外科学会理事長の大森孝一教授は、人工内耳技術の発展について語った。
「1978年に最初の人工内耳ができ、日本では1985年に東京医科大学で最初の手術が行われました。現在、国内では年間1200件程度の人工内耳手術が行われ、世界では100万人が装着しています」。
また、昨年から静岡県で、シェパードセンターと協力した新たな取り組みが始まっていることも紹介された。オーストラリアは人工内耳の普及率が日本の約4倍、小児においても2倍以上という実績があり、学ぶべき点が多いという。
「特に、早期介入に基づく聴覚活用型療育プログラムでは、小学校入学までに健聴児と同等の言語能力を身につけられるよう設計されています。オーストラリアでは、この支援体制の確立に至るまで約25年の歳月を要したとのことですが、日本においても、こうした先進的な取り組みに少しでも早く追いつくことができればと考えています」。
 大森教授に続いては、シェパードセンターのCEO アリーシャ・デイビス博士が登壇。オーストラリアの聴覚障害者支援システムについて詳しく説明した。
大森教授に続いては、シェパードセンターのCEO アリーシャ・デイビス博士が登壇。オーストラリアの聴覚障害者支援システムについて詳しく説明した。
「オーストラリアでは、親が子どもに聴覚障害があることに気づく前から支援が始まります。ほぼすべての新生児が生後数日以内に検査を受け、聴覚障害を持つ子どもの94%が、生後3ヶ月以内に診断されています」。
現在、オーストラリア全土で約1,000の家族と協力しており、プログラムを修了した子どもたちの大部分が、聴覚に問題のない子どもたちと同等の言語能力を身につけ、通常の学校に通い、キャリアを築いているという。
「重要なのは、早期検査と技術へのアクセスという要素を組み合わせることだ」と、デイビス博士は強調する。「システムは完璧ではありませんが、早期発見、迅速な対応、家族への支援、そして協力することで、子どもの可能性を最大限に引き出すことができます」。
イベントでは、実際に人工内耳を装用している子どもたち自らが自分の体験を語る時間も用意された。小中高それぞれの子どもたちと、当事者で、支援団体創設者でもある池田優里さんが語った話をダイジェストで紹介する。
 「私は、耳が聞こえません。赤ちゃんの時の検査で難聴だと分かりました。そして1歳の時、人工内耳の手術をしました。お父さんとお母さんは手術をするかとても悩んだけれど、今こうやってたくさんの人とおしゃべりをしたり、いろいろな音を楽しむことができてとっても幸せです」。
「私は、耳が聞こえません。赤ちゃんの時の検査で難聴だと分かりました。そして1歳の時、人工内耳の手術をしました。お父さんとお母さんは手術をするかとても悩んだけれど、今こうやってたくさんの人とおしゃべりをしたり、いろいろな音を楽しむことができてとっても幸せです」。
知花さんは地域の小学校に通い、難聴学級で国語と算数を、他の教科はクラスのみんなと一緒に勉強している。ピアノとスイミングの習い事もがんばっているという。「学校では絵が得意なので、図工が一番好きです。将来の夢は漫画家になること。作品を通じて、聴覚障害のことを、たくさんの人に知ってもらいたい」と明るく語った。
 「手術の後は、言語聴覚士の先生から言葉や発音の指導を受け、家でも朝から毎日勉強をしました。ろう学校に1年間通い、手話や指文字も覚えました。私は少しずつ話せるようになり、姉と一緒に小学校に通い始めました」。
「手術の後は、言語聴覚士の先生から言葉や発音の指導を受け、家でも朝から毎日勉強をしました。ろう学校に1年間通い、手話や指文字も覚えました。私は少しずつ話せるようになり、姉と一緒に小学校に通い始めました」。
 「私にとって人工内耳はあって当たり前のもので、なくては困るものです。私の通う高校のバイリンガルコースには、幼稚園小学校から一緒に通っている生徒が7割ほどいます。彼らにとっても私の人工内耳は当たり前の存在です」。
「私にとって人工内耳はあって当たり前のもので、なくては困るものです。私の通う高校のバイリンガルコースには、幼稚園小学校から一緒に通っている生徒が7割ほどいます。彼らにとっても私の人工内耳は当たり前の存在です」。
花さんは、コロナ禍でのマスク生活で口元を読みづらくなったことや、こしょこしょ話の聞き取りの難しさ、聞き取りを心配される英語よりも数学が苦手なことなど、リアルな体験を率直に語った。
「もしかしたら、これから先、自分は聴覚障害者であることを強く実感させられるときがくるかもしれません。でも、人工内耳を使っている人は、苦労している特別な生活を送っているというイメージを持たれがちですが、私の日常はいたって普通です。普通に話して普通に笑って普通に生きられています」。
 「私は1歳で右耳、12歳で左耳に人工内耳をつけたことが人生を大きく変えました。音のある世界を知って音楽を楽しみ、海外留学もできました」。
「私は1歳で右耳、12歳で左耳に人工内耳をつけたことが人生を大きく変えました。音のある世界を知って音楽を楽しみ、海外留学もできました」。
池田さんは音を理解するのに時間がかかり、「見る」「聞く」「感じる」体験を何度も重ねて音を理解してきたこと。言語聴覚士が母に「言葉で説明してあげてください」と言ってくれたことで、母は伝わる日がくると信じて説明してくれるようになったこと。「音に意味がある」と教えてくれたエピソードなどを語った。
現在は、難聴者と健聴者の相互理解を深めるための一般社団法人「Bridge Heart」を立ち上げ、SNS、講演活動など、積極的に活動する池田さん。
「聞こえないことはハンデだといわれます。でも壁のように見えるものも新しいことへの扉、可能性への入口かもしれません。不安の中にあるお子さん、お母さん、夢を持ち続けてください」と呼びかけた。
 第二部の冒頭は、自由民主党難聴対策推進議員連盟会長 上川陽子衆議院議員が登壇。2019年12月、議員連盟が「日本聴覚ビジョン」を策定し、聴覚障害者のライフサイクルに応じた支援措置とインフラの強化を政府に提案したこと。このビジョンに基づき、政府は新生児聴覚スクリーニングの促進や、補聴器・手話通訳支援などの施策を着実に実施している現状が語られた。
第二部の冒頭は、自由民主党難聴対策推進議員連盟会長 上川陽子衆議院議員が登壇。2019年12月、議員連盟が「日本聴覚ビジョン」を策定し、聴覚障害者のライフサイクルに応じた支援措置とインフラの強化を政府に提案したこと。このビジョンに基づき、政府は新生児聴覚スクリーニングの促進や、補聴器・手話通訳支援などの施策を着実に実施している現状が語られた。
また、上川議員の地元である静岡県では、聴覚障害児のリハビリテーションシステムの強化と方法の確立に積極的に取り組んでいると説明。この取り組みの一環として2024年11月、静岡県の機関とオーストラリアのシェパードセンターが、聴覚障害のリハビリテーションと教育に関するモデルプロジェクト協定を締結したことを発表した。
このプロジェクトでは今後3年間、毎年約10名の聴覚障害児にリハビリテーションプログラムを提供し、合計30名の子どもたちを支援する予定となっている。
「今年から開始されるこのプロジェクトを全国で推進できることを誇りに思います。聴覚障害を持つ子どもたちのために、さまざまな可能性を開いていくことを支援し続けたい」と締めくくった。
 シドニーから来日したダニー・アッカリさんと、小学生のオリバー・アッカリくん親子は、早期介入の体験を共有した。オリバーくんは3週間早く生まれ、生後数日で新生児聴覚スクリーニング検査を受けた。
シドニーから来日したダニー・アッカリさんと、小学生のオリバー・アッカリくん親子は、早期介入の体験を共有した。オリバーくんは3週間早く生まれ、生後数日で新生児聴覚スクリーニング検査を受けた。
「家族に聴覚障害の歴史がなかったので、まったく心配していませんでした。しかし、両耳とも反応がないことを告げられ驚きました」とダニーさんは当時を振り返る。
手話に焦点を当てる支援団体と、「聞くこと・話すこと」の発達に焦点を当てるシェパードセンターという2つの選択肢を検討した結果、シェパードセンターを選択。オリバーくんは生後6週間から通い始め、2017年1月に両側の人工内耳手術を受けたという。手術に成功し、問題なく回復している。
オリバーくんは、「今はランニング、コンピューターゲーム、映画鑑賞を楽しんでいます。音楽を聴いたり動画を見たりする時は、デバイスに直接接続できるので、音がとてもクリアです」と笑顔で語った。
イベントの最後には、シェパードセンター CEO アリーシャ・デイビス博士が再び登壇。 登壇者ならびに参加者に感謝を述べると共に、今後もオーストラリア、日本という国の枠を超えて、厚く協力していく約束がなされた。
 改めて、今回のイベントの意義と意味とは、どのようなものだったのだろうか。イベント終了後、シェパードセンター CEO アリーシャ・デイビス博士に聞いた。
改めて、今回のイベントの意義と意味とは、どのようなものだったのだろうか。イベント終了後、シェパードセンター CEO アリーシャ・デイビス博士に聞いた。
 今回のイベントを通して、日本の皆様と深い対話ができたことを嬉しく思います。聴覚障害を持つ子どもたちが語った体験談は、私たちの活動の意義を改めて実感させてくれました。
今回のイベントを通して、日本の皆様と深い対話ができたことを嬉しく思います。聴覚障害を持つ子どもたちが語った体験談は、私たちの活動の意義を改めて実感させてくれました。
シェパードセンターでは50年以上にわたり、音声言語によるコミュニケーション能力を育むための独自のアプローチを展開してきました。子どもが難聴として診断されるときは、医療・サポート以上のものが家族に対して必要です。私たちは子どもが診断されてすぐ、村のように家族のように、家族をひっくるめてサポートを提供しています。
よく誤解されやすいのですが、補聴器や人工内耳がついていると、子どもは自然に言語を習得できると思われがちです。しかしそうではありません。もともと子どもには言語がありませんので、言語療法士などの専門家が言葉や音の理解をサポートし、親御さんが日常生活の中で言語習得を促すような戦略を実践することが重要なのです。
早期介入については、生後1ヶ月までに診断がされ、生後2ヶ月までに補聴器や人工内耳がつけられる場合は、健聴児と同じような言語能力を習得できるようになります。赤ちゃんが生後6ヶ月までに人工内耳の手術をすれば、言語の習得ができます。早ければ早いほど良いということです。
また、私たちは10年ほど静岡県と連携していますが、お互いに学び合う関係を築いています。オーストラリアのプログラムをそのまま日本で使おうとするとうまくいかない場合もあるため、どの部分が日本の教育や保険制度に適用できるかを理解しようとしています。
例えば、オーストラリアにはオージオロジスト(Audiologist)と言語療法士(Speech Pathologist)という2つの職業がありますが、日本では言語聴覚士がその役割を果たしており、そのノウハウを日本のチームに伝えています。
私たちにとって、子どもたちとその家族が中心的な存在です。オーストラリアでは難聴者として生まれる子どもたちの90%が聞こえる親の元に生まれるため、親には新しい学びがたくさんあります。
私たちが家族の皆様にお伝えしたいのは、可能性は無限大だということ。難聴者であっても可能性がたくさん存在し、なんでもできるということです。AIや先端技術を取り入れることで、その可能性がさらに拡大すると確信しています。
オーストラリアと日本の協力により、より多くの子どもたちに選択肢を提供できることを確信しており、すべての難聴児とそのご家族が、自分に合った選択肢を自由に選べるよう、私たちは支援を続けてまいります。
このイベントを通して見えてきたのは、聴覚障害を「制限」ではなく「可能性への扉」として捉える新しい視点だった。早期発見・早期介入の重要性、家族を含めた包括的支援、そして子ども自身の選択を尊重するアプローチ。
これらの要素が組み合わさることで、聴覚障害を持つ子どもたちが、「普通に話して普通に笑って普通に生きられる」未来が実現できる。そのことを、イベントに参加した多くの人々が実感した一日となったのではないだろうか。今後もシェパードセンターをはじめ、聴覚障害者への取り組みに注目したい。
写真:松尾夏樹
文:笹間聖子