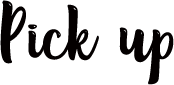2024.01.31
子どもがダメと言っても聞かないとき「親がやりがちな行動」と「声かけのコツ」

2025.04.25

子どもを育てる上で、ほめて伸ばすことが良いという考えは、近年ますます一般的に受け入れられてきました。適切にほめることで、子どもが自信を持ち、新しいことに挑戦する意欲を引き出せるといわれています。
でも、実際に「適切」なほめ方とは何でしょうか。ほめ方にも色々なアプローチがあり、「すごいすごい」「天才!」といったほめ方が良いのか、それとももっと別の方法があるのか。今回は、ほめ方の違いが子どもにどのような影響を与えるのか、そして効果的なほめ方のポイントについて考えていきたいと思います。
まず、3つのほめ方の種類を紹介します。
おざなり褒めとは、特に具体的な内容がなく「すごい!」「偉いね!」といった適当なほめ方です。一見ポジティブに聞こえるものの、何がどのようにすごいのかについての具体性がないため、子ども自身も何が評価されているのかを理解しにくいことが多いです。
人中心ほめは、子どもの性格、能力、見た目にフォーカスしたほめ方です。例えば、「頭がいいね」「優しいね」「かわいいね」といった表現が代表的です。これは、子どもの生まれ持っている内面的・あるいは外的な特質を評価するようなほめ方となります。
プロセスほめは、結果ではなくその過程や努力に焦点を当てたほめ方です。「一生懸命頑張ったね」「工夫していたところが素晴らしいね」といった表現がこれに当たり、子どもに対する励ましともいえます。このほめ方では、成功か失敗かという結果にかかわらず、そのプロセスでの努力や工夫を認めることを大切にしています。
それぞれのほめ方が、子どもにどのような影響を与えるのでしょうか?
おざなりほめばかりを続けると、子どもが外的評価を基準に自分の価値を見出すようになり、常に周囲からのほめ言葉を求める「ほめられ依存」になってしまう恐れがあります。
「ねえ、すごい?」とお子さんに何度も聞かれた経験がある方も多いのではないでしょうか? ひょっとしたら、気づかないうちに子どもが「すごい」とほめられることに慣れ、「ほめられ待ち」になっている可能性があります。
さらに、何が良かったのかが具体的に伝わらないため、何をほめられているのか、あるいは次にどうすればよいのかがわからず、成長の機会を逃すこともあります。
人中心ほめは、子どもにプレッシャーを与えてしまう場合があります。「あなたは頭がいいからね」といつもほめられていると、子どもはその評価を落とさないためにも、新しいことに挑戦することを避ける傾向が出てくるかもしれません。失敗を恐れて自分の限界を試さず、安全な選択をするようになってしまうことがあるのです。
また、失敗したときに「自分はもう頭がよくない」と自己評価を下げてしまうこともあります。
一方、プロセスほめは、結果に依存せず、努力や工夫を励ますほめ方なので、チャレンジ精神が育ちやすくなります。子どもは失敗を恐れず、努力を重ねることがいいことだ、と考えるようになります。
これにより、長期的な成長を目指して頑張ろうとし続ける姿勢が生まれます。外的な評価に頼ることなく、自分自身の努力を大切にし、チャレンジを恐れない子どもへと成長する可能性が一番高いほめ方だといえるでしょう。
 効果的なほめ方には、いくつかのポイントがあります。3つのコツを押さえることで、子どもにとってもっと良い影響を与える他、親子関係にもポジティブな影響があります。
効果的なほめ方には、いくつかのポイントがあります。3つのコツを押さえることで、子どもにとってもっと良い影響を与える他、親子関係にもポジティブな影響があります。
ほめる時、結果ではなく過程に目を向けましょう。例えば「100点取って天才だね」と言うよりも「100点を取るために、コツコツと努力していたものね」と言うことで、子どもが努力の大切さを感じることができます。これにより、子どもは結果に左右されず、どんなときも自分の成長を目指して頑張れるようになります。
子どもが何かに取り組んでいるとき、実際に目にしたことをそのまま伝えるのも効果的です。
例えば「いろんな色を使っているね」「〇〇ちゃんと同じ高さまで積み木を積んだんだね」といった具体的な観察を言葉にすることで、子どもは大人が自分の行動をしっかりと見てくれていることを感じ取ります。これにより、子どもは自分が認められているんだという安心感を持つことができます。
ほめるという行為は、そもそも大人から子どもへの一方的な評価となりがちです。そこで、子どもとの対話を促すために「質問」をすることも効果的です。
「一番頑張ったことは何だった?」「どこが一番好きなところ?」といった質問は、子ども自身が自分の行動や感情を振り返るきっかけになります。こうした質問から始まるコミュニケーションは、親子の関係を深めるだけでなく、子どもの言語能力アップにもつながります。
ほめることは、子どもの成長に大きな影響を与えます。しかし、どのようにほめるかによって、その効果は大きく異なります。おざなりなほめ方や人中心のほめ方は、子どもに外的評価に依存させたり、プレッシャーを与える可能性があります。
一方で、プロセスにフォーカスしたほめ方は、子どもの努力や工夫を認めることで、長期的に成長していく力を育てることができます。子どもが周囲からの評価や結果ばかりに気を取られることなく、自分自身の成長とそのための努力に目を向けられるよう、私たち大人自身が言葉に気をつけていきたいものです。
島村華子
 オックスフォード大学修士・博士課程修了(児童発達学)。日本人で唯一の、モンテッソーリ&レッジョ・エミリア教育の二つを司る研究者。現在はカナダの大学にて幼児教育の教員養成に関わりながら、日本でも教育・子育てについて、親や教育者に寄り添ったアドバイスを発信している。著書『アクティブリスニングでかなえる最高の子育て(主婦の友社)』『自分でできる子に育つ ほめ方 叱り方(ディスカヴァー・トゥエンティワン)』『親子でできる モンテッソーリ教育とマインドフルネス(創元社)』SNSでもホットな情報を発信中!
オックスフォード大学修士・博士課程修了(児童発達学)。日本人で唯一の、モンテッソーリ&レッジョ・エミリア教育の二つを司る研究者。現在はカナダの大学にて幼児教育の教員養成に関わりながら、日本でも教育・子育てについて、親や教育者に寄り添ったアドバイスを発信している。著書『アクティブリスニングでかなえる最高の子育て(主婦の友社)』『自分でできる子に育つ ほめ方 叱り方(ディスカヴァー・トゥエンティワン)』『親子でできる モンテッソーリ教育とマインドフルネス(創元社)』SNSでもホットな情報を発信中!
●X:@hana_shimamura
●インスタ:@hanako_shimamura_phd
FQ Kids VOL.20(2024年秋号)より転載